本日から新年度の行事が始まりました。今日は在学生向けのガイダンスがあり、新2年生が総合科目や資格科目をはじめとした様々な科目の履修について説明を受けました。
その後、新2年生を連れ出して図書館の専門書コーナーでガイダンスを行うゼミや、向かいの外濠公園でお花見を行うゼミもあり、さっそくゼミの先輩と親睦を深める姿が見られました。生憎、桜はまだ蕾の状態ですが、桜よりも一足早く先輩との会話に花が咲きました。
2011年度学位記交付式 祝辞・答辞・送辞
2012年3月24日に行われた日本文学科学位記交付式における祝辞、答辞、送辞の動画をお届けいたします。
堀江拓充先生からのご祝辞です。堀江先生もこの3月で法政大学を退職されました。
在校生代表として、関口雄士さんが送辞を述べました。
祝辞・送辞を受け、丸山瑞穂さんが卒業生代表として答辞を述べました。
あらためて、卒業生の皆さんのご多幸とご活躍を心よりお祈り申し上げます。
※動画には、プライバシー保護のため、一部、モザイク処理を施したところがあります。また、画像が大きく揺れる箇所があります。お許し下さい。
大学院 学位記授与式が行われました
2012年3月25日 | Author: dkoakimt
3月24日(土)、法政大学大学院の学位記授与式が行われました。本年度、日本文学専攻では修士13名、博士5名(課程博士3名、論文博士2名)が修了しました。修士論文・博士論文執筆に向けての研究には様々な困難があったことと思いますが、今後はその成果を学界や社会に向けて広く発信することが期待されます。修了者の皆さんの一層のご活躍を祈っています!
学位記授与式、卒業生を励ます会
2012年3月24日 | Author: odani
本日、日本武道館にて学位記授与式が行われ、その後844教室にて日本文学科の学位記授与式が行われました。生憎今朝は小雨が降っていましたが、武道館を出る頃には空も晴れ渡り、文字通り「晴れの門出」にふさわしい天気になってくれました。
学位記授与式の後は、スカイホール(ボアソナードタワー26階)にて「卒業生を励ます会」が催され、大勢の卒業生が集い、4年間を一緒に過ごした友との別れを惜しみました。雲が晴れたおかげで、スカイホールの窓からは開業間近の東京スカイツリーも綺麗に見ることができました。
恩師や友人達との記念撮影をはじめ、ゼミ単位でのスピーチ、小秋元先生による特別卒業試験(?!)のサプライズなどで会は大いに盛り上がり、最後は全員で輪になって校歌を合唱しました。その時の動画は以下でご覧頂けます。(ただし、プライバシーに配慮して解像度を極端に低く設定してあります。)
『日本文學誌要』第85号発刊
2012年3月21日 | Author: odani
『日本文學誌要』第85号が今月24日に発刊されます。本号は立石伯特集です。今月末をもって法政大学文学部を退職なさる堀江拓充教授(筆名:立石伯)の特集号ということで、多くの方から寄稿頂きました。立石伯主要著作目録もございますので、皆さま是非ご覧下さい。
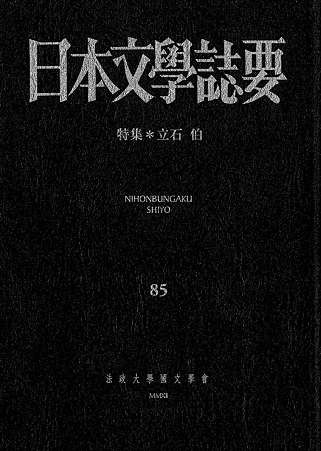
shiyo_85 posted by (C)法政日文
目次
〈講 演〉
文学の力について─文学は何をなし得るか─ 立石 伯
〈論 文〉
高橋和巳の〈文学〉概念─「文学の責任」をめぐって─ 藤村耕治
王道楽土の夢、「河向う」の幻─中薗英助「密作者」─ 戸塚麻子
紙の月/埴谷雄高と西田幾多郎2
─「わたし/あなた」という大調和の夢─ 山田 稔
村上春樹「井戸」再考 武井昭也
〈思い出〉
心の負債 宮内豊
阻石の寂蓼──現視のなかの立石伯 齋藤愼爾
鎧と安来節 岡嶋 稔
酒と泪と先生と私 染谷結花
堀江先生の思い出 福田真顕
三分咲きの『西行桜』記 李 忠奎
堀江先生への感謝、そして立石伯氏へ 関口雄士
〈目 録〉
立石伯主要著作目録 藤村耕治
〈卒業論文〉
菅原道真〈菊〉詩論 樋野あゆみ
『源氏物語』独詠歌論 穂積芙雪
催馬楽《鷹山》・《此殿》グループと唐楽《西王楽》の成立について
─二重の同音性が物語ること─ 宮崎めぐみ
〈彙 報〉
〈法政大学国文学会会則〉
〈投稿要項〉
加藤昌嘉准教授の著書『揺れ動く『源氏物語』』(勉誠出版)が第13回紫式部学術賞に
加藤昌嘉准教授の著書 『揺れ動く『源氏物語』』 (勉誠出版)が第13回紫式部学術賞を受賞しました。社団法人紫式部顕彰会のサイトによると、受賞式と講演会は以下のような日程で行われるとのことです。
・日時: 5月12日(土) 14:00~16:00
・場所: 京都商工会議所 3階講堂
・参加: 無料
学位授与式、卒業祝賀パーティの詳細決定
2012年2月19日 | Author: odani
学位授与式当日の日程(PDF)が確定しました。日本文学科は以下の通りです。4年間を共に過ごした仲間と恩師が一堂に会して語らう最後のチャンスですから、卒業生の皆さんは夕方の卒業祝賀会にもぜひ参加して下さい。
学位授与式 (文学部は「午後の部」です)
日時: 2012年 3月 24日(土) 13:00 開場 13:45 開式
場所: 日本武道館
学位記交付
時間: 16:00~17:00
場所: 844教室
卒業祝賀会
時間: 17:30~19:30
場所: ボアソナードタワー 26階 スカイホール
費用: 無料
『「作家特殊研究」研究冊子1 絲山秋子』を刊行
2012年1月19日 | Author: odani
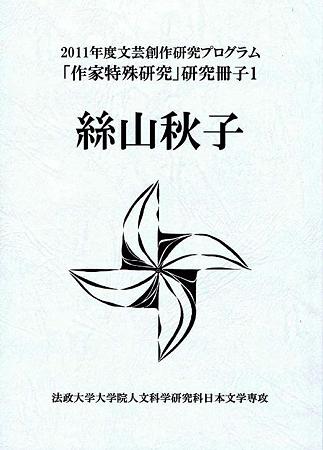 法政大学大学院人文科学研究科日本文学専攻では、2011年度から「文芸創作研究プログラム」という特別プログラムを開設しております。その基幹科目である「作家特殊研究」の教育研究活動の一環として、『「作家特殊研究」 研究冊子1 絲山秋子』を発刊しました。本科目は、第一線で活躍なさっている文芸創作家を講師にお迎えし、院生達がその作家の作品を取り上げ作家自身の前で研究発表を行うという、非常に画期的な授業です。本冊子には、この科目を通じて作家と大学院生が対話と議論を重ねた末に練り上げられた論考9編に加え、インタビュー、基礎資料、エッセイなどが納められています。
法政大学大学院人文科学研究科日本文学専攻では、2011年度から「文芸創作研究プログラム」という特別プログラムを開設しております。その基幹科目である「作家特殊研究」の教育研究活動の一環として、『「作家特殊研究」 研究冊子1 絲山秋子』を発刊しました。本科目は、第一線で活躍なさっている文芸創作家を講師にお迎えし、院生達がその作家の作品を取り上げ作家自身の前で研究発表を行うという、非常に画期的な授業です。本冊子には、この科目を通じて作家と大学院生が対話と議論を重ねた末に練り上げられた論考9編に加え、インタビュー、基礎資料、エッセイなどが納められています。
本冊子の企画・編集は「作家特殊研究」の受講生によって行われておりますが、絲山秋子先生のご協力無くしては本冊子の完成はありませんでした。本科目を通じて受講生を熱心にご指導下さいました絲山先生に、この場をお借りして篤く御礼申し上げます。
『はじめての日本神話 『古事記』を読みとく』(坂本勝著、ちくまプリマー新書)が出版されました
2012年1月11日 | Author: odani
2012年1月10日に、『はじめての日本神話 『古事記』を読みとく』(坂本勝著、ちくまプリマー新書)が筑摩書房より出版されました。『古事記』がテーマということで、非常に難解な印象をお持ちになる方も多いと思いますが、本書は第一部が「あらすじで読む『古事記』 -神と人の物語」となっていますので、初学者も安心して読み進めることができる入門書です。後半の第二部は、「古代人が出会った〈自然〉 -神と人がまじわる場所」と題し、「水と生命」、「天と地」、「死と再生」、「内なる自然」といったテーマに分けて、『風土記』や『日本書紀』の神話も取り上げながら、神話の世界を読みといてゆきます。「自分たちの祖先は、この列島でどのように暮らしてきたのか、〈自然〉について〈文化〉について〈歴史〉について、どのように考えてきたのか、今の自分たちはそれをどのように受け止めて生きなければならないのか」(本書p.18)、こういった根源的な問いについて考えるヒントを探しながら、坂本教授が案内して下さる日本神話の世界をどうぞお楽しみ下さい。
「現役教師の話を聞く会」を開催しました
2011年12月23日 | Author: dkoakimt
12月22日(木)、「現役教師の話を聞く会」が開催されました。佼成学園中学・高等学校教諭の西田真悟先生(2003年度日本文学専攻修士課程修了)を講師に迎え、教師の日常、教師になるためのキャリア形成の方法、国語教師としてのやりがいなどを具体的に語っていただきました。特に、教育とは未来を作る仕事だととらえ、日々の仕事のなかで人を育てていることに手ごたえを感じているという西田先生の言葉は印象的でした。質疑応答も活発に行われ、将来、教職に就くことを考えている学生、大学院生には貴重な機会となりました。
日本文学科、大学院日本文学専攻では、本年度より教職をめざす学生のための支援事業をはじめました。本年度は5、6月に「教員採用試験対策特別講座」(講師:前草加南高等学校校長、伊古田陽子先生)、8月に「私学教員適性検査事前学習会」を行っています。今後も様々な企画で教員志望の学生の支援を行ってゆきたいと考えています。(報告者:小秋元段)









