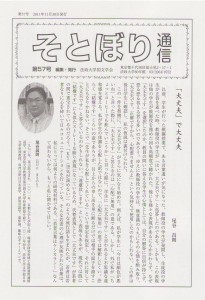2011年度の法政大学エクステンションカレッジ「大人のための古典文学」が、12月10日(土)に無事終了しました。最終回の講師は伊海孝充日本文学科専任講師です。
「水を司る龍―能〈河水〉―」というテーマで、自分の皇子を龍女の夫として差し出した天竺の皇帝が、龍女の加護によって危難を逃れ、国の平安を得るという能〈河水〉がとりあげられました。ビデオを交え、軽妙なトークに時を忘れる講座でしたが、この曲には自然を畏敬することにより自然に守られる、人間本来のあり方が描かれているとする締めくくりの言葉には、受講者の皆さんも深く納得しているご様子でした。東日本大震災復興のためのチャリティ講座としての最終回にふさわしい講座だったといえるでしょう。
また、今回は講座終了後、受講者の皆さんと講師による茶話会が催されました。普段の講座ではうかがえない、皆さんの文学に対する熱い思いをお聞きすることができ、大変有意義なひとときでした。宮城県より毎回参加された受講者の方からはお手製の干し柿がふるまわれ、おいしくいただきました。 (報告者:小秋元段)