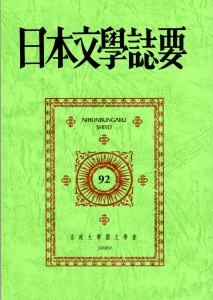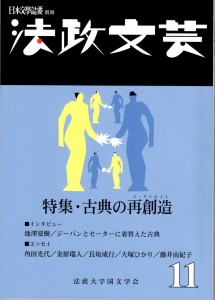『日本文學誌要』第92号が刊行されました
『日本文學誌要』第92号が刊行されました。
目次は以下の通りです。
〈研究ノート〉
『源氏物語』における絃楽器の曲種と調絃について
―古楽譜研究者の立場から―
(スティーヴン・G・ネルソン)
“橘の小島”に橘の木はあったか
―『源氏物語』「浮舟」巻の状景―
(藤井輝)
〈資料紹介〉
日本文学科の古典籍(一三)(小秋元段)
〈随想〉
トキワ荘と「漫画少年」(山田夏樹)
〈卒論〉
浮舟は妊娠していたか
―『源氏物語』における不義の子―(新明美寿穂)
百物語系怪談集から考える「怪異」への意識(工藤亜美)
谷崎文学における『竹取物語』受容
―『細雪』に刻まれた暗号(エニグマ)―(鈴木千祥)
〈連載〉
私の卒業論文(3)(藤村耕治)
〈追悼〉
笠原先生追悼(中沢けい)
〈修論題目一覧〉
〈卒論題目一覧〉
〈通教卒論題目一覧〉
〈会則・投稿要項〉
〈編集後記〉
『法政文芸』第11号が刊行されました
『法政文芸』第11号が刊行されました。
目次は以下の通りです。
〈巻頭詩〉
風景 小林坩堝
〈巻頭エッセイ〉
民主と愛国 温又柔
【創作】
〈小説〉
マリアへ捧ぐ眼 飯村桃子
群青の石 北吉良多
グラヴィティ 武田航希
あの町、この町 升井梨恵
さくら 峯岸菜々子
〈掌編セレクション〉
東京ドールズエクソダス 岡村一慶
剥片拾い 亀田安土
夏と月と凍りの夜 瀬崎朱里
Ha_ru_e 三好裕美
【特集】古典の再創造(リ・クリエイト)
〈インタビュー〉
ジーパンとセーターに着替えた古典 池澤夏樹
〈エッセイ〉
それが残っている理由 角田光代
新訳の意義 金原瑞人
古典文学と現代語訳 長坂成行
楽しみながら、疑いながら…… 大塚ひかり
『かげろうの日記』の「私」 藤井由紀子
〈アンケート〉
時めく古典アンケート
〈学生レビュー〉
『古事記』/『源氏物語』/『徒然草』/『南総里見八犬伝』
〈点描〉
〈著者紹介〉
〈編集後記〉
オープンキャンパスが開催されました
 去る8月2日(日)、今年度第1回目の市ヶ谷のオープンキャンパスが実施されました。学部・学科ごとに説明会や模擬授業が行われ、学生による展示とともにさまざまな角度から工夫を凝らして大学での学び、学生生活に触れる機会を提供しました。
去る8月2日(日)、今年度第1回目の市ヶ谷のオープンキャンパスが実施されました。学部・学科ごとに説明会や模擬授業が行われ、学生による展示とともにさまざまな角度から工夫を凝らして大学での学び、学生生活に触れる機会を提供しました。
文学部企画では、終日展示部屋にて各学科の概要や特色、教科書の展示を行っています。また学科生の生の声を伝える企画として、各学科説明会後にスタッフによる学生トークを行ったり、文学部の概要、文学部生の生活を載せたスタッフが作った冊子も配布したりしています。日本文学科では10:00から学科説明会で教員と学生の視点から日本文学科の学びを紹介したあと、11:05から尾谷先生による模擬授業「〈比喩〉のない人生なんて考えられない!」が行われました。
 個人的には今年初めて学科説明会での学生トークを行い、来てくださった方々に学科のことや学生生活など、学生目線でお話しできたことが印象的です。教室が埋まるほどの大勢の方の前で話すのは緊張しましたが、自分の言葉で学科のことを伝えることにやりがいを感じました。スタッフとして2年目、今年最初のオープンキャンパスを無事に終えることができ、ひとまず安心しています。学科数が多い文学部では準備が大変な時期もありましたが、スタッフ一丸となって企画を作り上げ、6学科ある文学部の魅力を、来てくださった方々に十分にお伝えすることができたと思います。後半オープンキャンパスでも、より多くの方に学科のことをお伝えできればと思います。また、企画部屋でたくさんの方とお話しし、文学部のことを分かりやすくお伝えできるよう努めたいと思います。
個人的には今年初めて学科説明会での学生トークを行い、来てくださった方々に学科のことや学生生活など、学生目線でお話しできたことが印象的です。教室が埋まるほどの大勢の方の前で話すのは緊張しましたが、自分の言葉で学科のことを伝えることにやりがいを感じました。スタッフとして2年目、今年最初のオープンキャンパスを無事に終えることができ、ひとまず安心しています。学科数が多い文学部では準備が大変な時期もありましたが、スタッフ一丸となって企画を作り上げ、6学科ある文学部の魅力を、来てくださった方々に十分にお伝えすることができたと思います。後半オープンキャンパスでも、より多くの方に学科のことをお伝えできればと思います。また、企画部屋でたくさんの方とお話しし、文学部のことを分かりやすくお伝えできるよう努めたいと思います。
8月後半、23・24日のオープンキャンパスへ向けて、現在もスタッフで準備を進めています。今年度は6学科の比較を交えた6学科横断トークショーも行います。「法政大学の文学部」では何ができるのかを簡単に知ることができる企画となっていますので、ぜひ足を運んでいただけたらと思います。また、説明会後の学生トーク、展示、冊子等、文学部の魅力をお伝えする企画を準備しています。文学部企画展示部屋で、スタッフ全員、みなさまのご来場をお待ちしております。
(日本文学科2年/文学部企画スタッフ 川瀬亜子)
国立劇場キャンパスメンバーズ9月対象公演
国立劇場キャンパスメンバーズの9月対象公演の情報です。
チケットは8月上旬にチケットが発売になります。
9月は国立劇場小劇場で文楽公演が行われる月です。5月の文楽公演は吉田玉男さんの襲名興行ということもあり、チケットは即日完売状態でした。特別な興行に限らず、文楽のチケットは意外と早く売りきれるので、早めに予約しましょう。
電話か窓口での申込みです。学生証もお忘れなく。
9月の対象公演はこちら→9月予定
銀座金春祭りへのお誘い
 銀座には「金春通り」と呼ばれる場所があります。この名称は江戸時代、能役者の金春大夫の屋敷があったことに由来していますが、毎年8月1〜7日までここで「金春祭り」が行われています(7月31日前夜祭)。7日の路上能がメインですが、能楽に関わる講座も開催されています。今年は伊海ゼミでこのお祭りのお手伝いにうかがいます。また能に親しみのない方々のために、左のパンフレットを作成し、能や金春通りの解説のほか、英語訳・中国語訳も作りました。パンフレットはお祭り期間中、会場周辺で配布されます。是非、お立ち寄りください。
銀座には「金春通り」と呼ばれる場所があります。この名称は江戸時代、能役者の金春大夫の屋敷があったことに由来していますが、毎年8月1〜7日までここで「金春祭り」が行われています(7月31日前夜祭)。7日の路上能がメインですが、能楽に関わる講座も開催されています。今年は伊海ゼミでこのお祭りのお手伝いにうかがいます。また能に親しみのない方々のために、左のパンフレットを作成し、能や金春通りの解説のほか、英語訳・中国語訳も作りました。パンフレットはお祭り期間中、会場周辺で配布されます。是非、お立ち寄りください。
(銀座金春通り会 http://komparu-ginza.com)
さて、すでにパンフレットに誤りがありますので、ここに訂正させていただきます。
【謡初図の中国語キャプション】
(正)江户城新年时的例行活动〈谣初〉。作为奖赏,能演员可受领到武士的衣装。
【「金春通りの歴史」の解説】
(誤)金春屋敷が1870年頃麹町に移転すると、屋敷跡地に
(正)江戸時代後期に金春大夫の住まいが麹町に移ると、屋敷地に
またシテ方金春流宗家の金春安明先生がこのパンフレットを丁寧にご覧になってくださり、「江戸時代の能役者を町人と限定するのは言い過ぎではないか」というご批判を寄せてくださりました(上記に誤りもご指摘)。
江戸時代の能役者は「武士」ではありませんでしたが、それに準ずるような扱いを受ける者もいたので、ご指摘どおり「町人」と限定するのは正しくありません。能役者は『武鑑』という武士の目録にも名前が載っていたので、士分に近い身分だったといえるでしょう。。その「待遇」の一例が金春通りに関わる拝領屋敷です。
江戸は武家地と町人地とが厳密に別れていましたが(人口増加などの影響で、幕末には区分が崩れる)、後者に拝領された敷地を「拝領町屋敷」と呼びます。能役者が幕府から賜った屋敷はこの「拝領町屋敷」です。武家地の拝領屋敷とは異なり、「拝領町屋敷」は自分が住まず、町人などに貸すこと(アパート経営のようなもの)ができました。法政大学能楽研究所には小鼓役者が賜った屋敷図が所蔵されていますが、地図上には細かな賃料まで記載されています。金春屋敷もそのようにして、町人たちの住まいとなっていきました。
パンフレットは字数の制限もあったので、誤りの訂正とともに補足説明させていただきました。金春安明先生、ありがとうございました。
杉本圭三郎先生がご逝去されました
日本文学科で教鞭をとられた後、法政大学国文学会会長としてご尽力されてこられた杉本圭三郎先生(本学名誉教授)が、7月10日(金)に享年88歳で永眠されました。
誠に痛恨の情にたえません。
通夜及び葬儀、告別式は下記によりとり行われます。
謹んでご冥福をお祈りするとともに、お知らせ申し上げます。
・通夜 7月16日(木)18:00~19:00
・告別式 7月17日(金)10:00~11:00
・会場 シティホール中野坂上(中野区本町1-25-8、電話:03-5302-1194)
・喪主 妻 杉本和子様