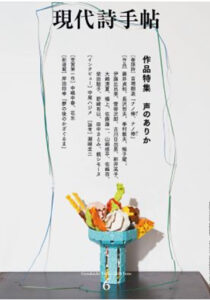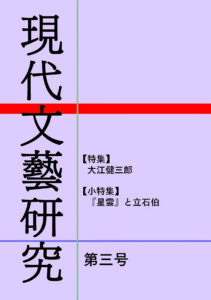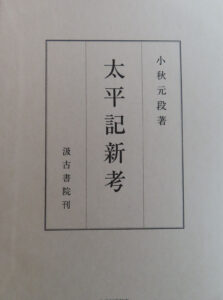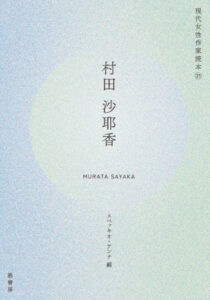2024年6月20日、黒田真美子先生(日本文学科元教授)が編者をつとめた『中国/日本〈漢〉文化大事典』が、明治書院より刊行されました。
2024年6月20日、黒田真美子先生(日本文学科元教授)が編者をつとめた『中国/日本〈漢〉文化大事典』が、明治書院より刊行されました。
同書には、遠藤星希先生(日本文学科准教授)が寄稿されています。
中国・日本の文学・思想を学ぶ方々の必携書として編集されており、一般読者にも読みやすいように、専門用語・術語に頼らないわかりやすい解説となっております。
ぜひ、お手にとってご覧ください。
以下、書誌情報と目次は出版社サイトからの転載でございます。
○********○
【書誌情報】
発行:明治書院
発行日:2024年6月20日
書店発売日:2024年7月1日
定価:41,800円(38,000+税)
頁数:B5・952ページ
ISBN:9784625404108
【内容】
中国の伝統文化としての〈漢〉文化(文学・思想・芸術等)と、それを受容・展開した日本文化の深層に残る〈漢〉文化の総体を一冊に
- 中国編(先秦~近代、253項目)、日本編(上代~近代174項目)で構成
- 大項目・中項目により、「引く事典」であるとともに「読む事典」
- 専門用語・術語に頼らない、わかりやすい解説
- 付録:参考地図/日本と東アジア各国との交流年表
【目次】
収録項目
【中国編】
漢字(誕生・起源) 音韻学 暦 経書・経学 楽 訓詁学 目録学 叢書 総集 類書 科挙 出版文化 神仙 隠逸 三教一致 女性詩人 文学批評 文言小説 書 絵画 庭園 茶 先秦の文学・思想 神話・伝説 西王母 詩経 楚辞 周易 尚書 礼 春秋 論語 孝経 孔子 孟子 荀子 墨子 黄帝 老子 列子 荘子 韓非子 宗廟 陰陽五行 社 秦漢の文学・思想 賈誼 淮南子 賦 司馬相如 董仲舒 史記 列女伝 古詩 泰山 太一 巫 讖緯 揚雄 漢書 王充 説文 鄭玄 六朝の文学・思想 駢文 楽府 曹操 建安の七子 曹植 阮籍 嵆康 竹林七賢 三国志 潘岳 陸機 王羲之 山海経 志怪 捜神記 陶淵明 謝霊運 世説新語 鮑照 謝朓 沈約 竟陵の八友 文心雕龍 詩品 文選 玉台新詠 庾信 顔之推 水経注 荊楚歳時記 玄学 関羽 天師道 葛氏道 養生 洞天福地 道観 漢訳仏典 格義仏教 慧遠 菩薩 盂蘭盆 密教 浄土信仰 声明・梵唄 唱導文学 隋唐五代の文学・思想 王通 五経正義 石経 律令 貞観政要 則天武后 初唐四傑 陳子昂 劉知幾 近体詩 孟浩然 王昌齢 王維 高適 李白 顔真卿 杜甫 岑参 韋応物 伝奇 古文 韓愈 劉禹鍚 白居易 柳宗元 元稹 賈島 李賀 杜牧 李商隠 温庭筠 皮陸 変文 禅 科儀 宋代の文学・思想 文苑英華 太平広記 三清 玉皇 道蔵 范仲淹 欧陽脩 資治通鑑 王安石 蘇軾 黄庭堅 米芾 徽宗 詞 筆記 詩話 棠陰比事 岳飛 陸游 朱熹 朱子学 風水 城隍神 文昌帝君 媽祖 内丹 正一教 文章軌範 王応麟 文天祥 金元代の文学・思想 元曲 呉澄 散曲 全真教 明代の文学・思想 宋濂 高啓 白話小説 三国志演義 水滸伝 西遊記 金瓶梅 封神演義 文徴明 帰有光 王世貞 胡応麟 袁宏道 菜根譚 五雑組 三言二拍 馮夢龍 明曲 王守仁 陽明学 林兆恩 李贄 東林党 宝巻 八仙 漢文笑話 清代の文学・思想 顧炎武 王夫之 黄宗羲 銭謙益 金聖嘆 李漁 王士禛 聊斎志異 沈徳潜 紅楼夢 儒林外史 袁枚 紀昀 清朝考証学 朱彝尊 方苞 戴震 趙翼 銭大昕 章学誠 龔自珍 魏源 曽国藩 秋瑾 林紓 康有為 王国維 梁啓超 近代の文学・思想 文学革命 蔡元培 章炳麟 魯迅 周作人 胡適 郭沫若 茅盾 郁達夫 老舎 聞一多 巴金 張愛玲 民間故事
【日本編】
漢文学の受容と変容 中国観の変遷 漢文訓読・訓点 字書 類書 和歌と漢詩 歌学と詩論 書 唐絵 庭 漢籍の出版 上代の漢学・漢文学 聖徳太子 古事記 日本書紀 懐風藻 万葉集 遣隋使・遣唐使 平安時代の漢学・漢文学 六国史 嵯峨天皇 凌雲集 文華秀麗集 経国集 空海 文鏡秘府論 入唐求法巡礼行記 渤海使 小野篁 島田忠臣 菅原道真 日本国見在書目録 新撰万葉集 千載佳句 古今和歌集 句題和歌 漢文日記 仮名日記 平安朝物語文学 枕草子 源氏物語 本朝麗藻 和漢朗詠集 本朝文粋 類聚句題抄 類書 藤原忠通 今昔物語集 白氏文集 李嶠百詠 遊仙窟 蒙求 新撰字鏡 倭名類聚抄 類聚名義抄 願文 詩序 幼学書 往来物 大学寮 陰陽道 雅楽 鎌倉時代室町時代の漢学・漢文学 五山文学 栄西 道元 円爾 夢窓疎石 虎関師練 義堂周信 絶海中津 一休宗純 新古今和歌集 平家物語 太平記 徒然草 説話文学 孝子伝 謡曲 抄物 一条兼良 清原宣賢 詩歌合 和漢聯句 古文真宝 三体詩 聯珠詩格 金沢文庫 足利学校 墨蹟 水墨画 江戸時代の漢学・漢文学 雅俗 朱子学 藤原惺窩 林羅山 林家 木門 室鳩巣 新井白石 雨森芳洲 陽明学 中江藤樹 熊沢蕃山 古義学 伊藤仁斎 伊藤東涯 古文辞学 荻生徂徠 服部南郭 皆川淇園 懐徳堂 考証学 水戸学 昌平黌 寛政異学の禁 隠元 儒家神道 琉球の儒学 朝鮮通信使 唐話学 藩校 寺子屋 江戸漢詩 石川丈山 元政 唐詩選 大田南畝 都賀庭鐘 文人 詩社 詩話 市河寛斎 柏木如亭 広瀬淡窓 菅茶山 頼山陽 梁川星巌 菊池五山 大沼枕山 漢文戯作 仮名草子 狂詩 談義本 洒落本 読本 上田秋成 曲亭馬琴 本居宣長 俳諧 松尾芭蕉 与謝蕪村 老荘思想 白話小説 明治時代の漢学・漢文学 漢文教育 新聞・雑誌と漢文学 漢文小説・繁昌記 三島中洲 中江兆民 成島柳北 依田学海 中野逍遥 菊池三渓 森槐南 森春涛 野口寧斎 正岡子規 夏目漱石 森鴎外 幸田露伴 芥川龍之介 近代作家と漢文学