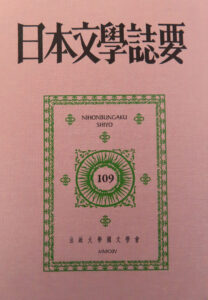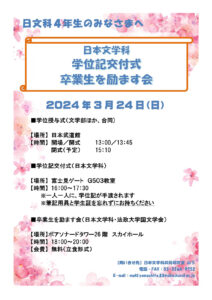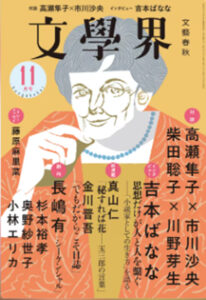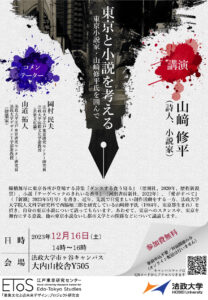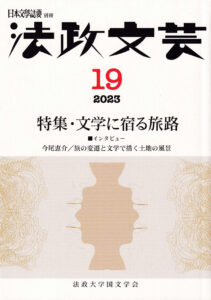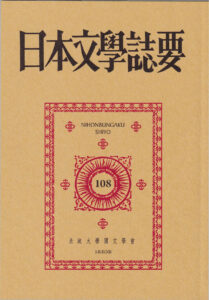2023年度学位授与式が、2024年3月24日(日)に日本武道館にて行われました。
https://www.hosei.ac.jp/pickup/article-20240328111332/
終了後、市ヶ谷キャンパスにて、日本文学科卒業生への学位記交付式セレモニーが行われました。まずは、2023年度いっぱいでご退任の三井喜美子先生より卒業生への祝辞が送られました。 その後、卒業生を代表して川俣穂菜美さん(山口ゼミ)より答辞が述べられました。また、文学部同窓会特別奨励賞として、松井凜さん(藤村ゼミ)が表彰されました。最後に、クラス別に学位記の交付が行われました。
その後、卒業生を代表して川俣穂菜美さん(山口ゼミ)より答辞が述べられました。また、文学部同窓会特別奨励賞として、松井凜さん(藤村ゼミ)が表彰されました。最後に、クラス別に学位記の交付が行われました。
18:00からは、ボアソナードタワー26階のスカイホールにて、日本文学科卒業祝賀会「卒業生を励ます会」が催されました。日本文学科では、新たな門出を迎えた卒業生を励ますために、法政大学国文学会と日本文学科学生委員会が中心となって「卒業生を励ます会」が伝統的に催されています。コロナ禍を経て、5年ぶりの開催となりましたが、学生委員会によるビンゴゲーム大会や教員による企画などで大いに盛り上がり、楽しく和やかな時間となりました。最後には、こちらも恒例行事の、全員で肩を組んでの校歌の大合唱!!4年間の思い出を、友や先生方と語りあい、盛会のうちに終了しました。卒業生を励ます会を企画してくださいました学生委員会の皆さま、ありがとうございました。