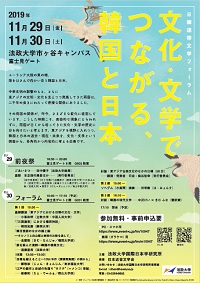法政大学市ヶ谷キャンパスにて、法政大学国際日本学研究所主催の日韓連携文学フォーラム、「文化・文学でつながる、韓国と日本」が開催されます。
詳細は下記のウェブサイトにてご覧ください。
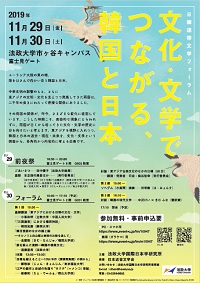
◆前夜祭◆
日時:11月29日(金)18:30~20:00
場所:法政大学市ヶ谷キャンパス 富士見ゲート6階 G602教室
ごあいさつ
田中優子(法政大学総長)
座談 本企画の趣旨ほか
〔実行委員会〕(五十音順)
加藤敦子(都留文科大学)・小林ふみ子(法政大学)・染谷智幸(茨城キリスト教大学)・
中沢けい(作家/法政大学)・韓京子(はん・きょんじゃ/青山学院大学)
◆フォーラム◆
日時:11月30日(土)10:00~17:10(予定)
場所:法政大学市ヶ谷キャンパス 富士見ゲート2階 G201教室
——————————————————————–
【第1部 10:00~】
基調講演「東アジアにおける日韓の文化・文学」
小峯和明(立教大学・中国人民大学)
『三国遺事』における檀君神話
袴田光康(静岡大学)
韓日芸能のなかの翁と嫗―タルノリと白山郷土芸能の比較を通して
金蘭珠(きむ・なんじゅ 檀国大学校)
茶を詠んだ漢詩―韓国の喫茶文化
遠藤星希(法政大学)
——————————————————————–
休憩 12:05~13:00
——————————————————————–
日韓を越えること―1764年作《蒹葭雅集図》の例から
鄭敬珍(じょん・きょんじん 東京福祉大学)
江戸の戯作と京城の色摺り”タクチ”(=メンコ)草紙
崔泰和(ちぇ・てーふぁ 群山大学校)
討論:東アジア古典文化のなかの日韓(50分)
講演・発表者 司会:染谷智幸〔実行委員会〕
——————————————————————–
【第2部 15:00~】
ソヘグム(小奚琴)演奏
河明樹(は・みょんす)
——————————————————————–
【第3部 16:10~】
対談:韓国の現代文学
中沢けい × きむ ふな(翻訳家)
——————————————————————–
17:10 閉会(予定)
■参加費
無料(どなたでも参加可能です)
■事前申込要 以下の申込専用フォームからお申込みください。
・PC/スマホ用 https://www.event-u.jp/fm/10947
・携帯(ガラケー)用 https://www.event-u.jp/fm/m10947
■交通 飯田橋駅,市ヶ谷駅より徒歩10分
【キャンパス・交通案内】 http://www.hosei.ac.jp/access/ichigaya.html
■主催 法政大学国際日本学研究所
■後援 日本近世文学会
■お問合せ先
法政大学国際日本学研究所事務室
E-mail:nihon@hosei.ac.jp
TEL :03-3264-9682
※詳細は、法政大学国際日本学研究所ウェブサイトにてご確認ください。