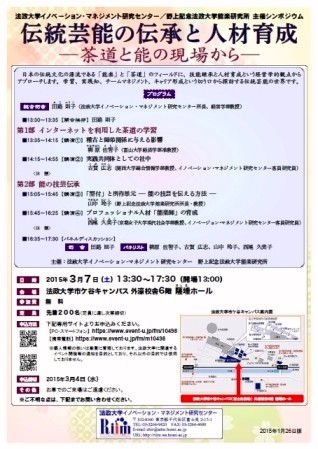「法政大学国文学会 教員のつどい」立ち上げ会のご案内
■日時:2015年 3月21日(土)15時00分~
■場所:法政大学ボアソナードタワー705教室
■会費:5,000円(国文学会年会費3,000円+交流会費2,000円)
■交流会:17時00分から別会場(交流会のみの参加も可能です)
■出席連絡用アドレス: hoseikokubunteacher(アットマーク)yahoo.co.jp
*****学校にて勤務の教員の方 各位*****
早速ですが、この度「法政大学国文学会 教員のつどい」の立ち上げ会を開催し、引き続き皆様方の情報交換を目的に交流会を催すことと相なりました。
当つどいは、校種や地域の垣根を越えて、教員同士の情報交換や意見交流を目的としています。
研究や授業実践を発表するような堅苦しい場ではありません。年1、2回程度、教員同士が集まり、日頃感じていることや現在の状況などを交流しあう場になればと思っています。立ち上げ会では、つどいの目的、運営方法、今後の予定などについて皆様のご意見を伺いながら、方針を決めていく予定です。
現段階では、法政大学国文学会(年会費/3,000円)にご参加頂き、国文学会会員として刊行物を受けとり、さらにつどいにて情報交換ができるという、教員としてメリットのある運営形態を考えています。皆様のご協力のもと、ひいては教員としての資質を向上する研修の場としても意味をもつような、有意義なつどいにしていければと思います。
また、『日本文学誌要』などに教員のためのページを設けることも、国文学会委員会の方で検討してもらっています。今後、教員生活をエッセイとして紹介したり、教材研究の新たな考察を掲載することも可能です。
授業づくり、生活指導、部活動で多忙とは存じますが、多くの方にご出席いただければ幸いです。
■呼びかけ人:北川俊(2009年卒・小秋元ゼミ)、中村奈央子(2010年卒・藤村ゼミ)、鈴木健吾(2010年卒・田中ゼミ)、赤在翔子(2011年院卒・田中ゼミ)、加瀬ひとみ(2011年卒・藤村ゼミ)、宮負竣(2013年卒・藤村ゼミ)
■窓口教員:藤村耕治、田中和生