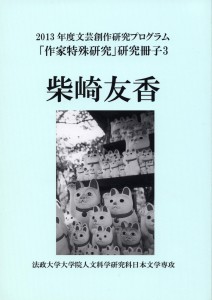去る10月21日から25日にかけて、スティーヴン・ネルソン教授、加藤昌嘉教授、小秋元段教授と半田朋之大学院課入試担当の4名が中国を訪れ、四川外国語大学、重慶師範大学、福州大学において大学院進学説明会と模擬授業を行いました。
法政大学大学院人文科学研究科は2012年から13年にかけて、この3大学と大学院特別入学試験の実施に関する協定を締結し、日本文学専攻と国際日本学インスティテュートの入試を現地で実施することになりました。入試は4年生を対象に毎年3月に行われ、合格者は卒業(6月)後の9月に特別研修生として法政大学大学院に在籍し、修士課程に入学するための事前研修を受けることになっています。現在、中国では日本の大学院に進学を希望する学部卒業生が増えています。本研究科の取り組みはこうした要望に応えるもので、現地入試と事前研修を一体化することにより、留学生が日本の大学院での学修に円滑に移行できることをめざして開始されました。
各大学では、日本への留学に関心をもつ多くの学生が参加し、教職員による説明に熱心に耳を傾けていました。そして、説明会終了後は日本の大学院における授業の様子や教員の指導方法、奨学金制度をはじめとする留学生活などをめぐり、活発な質疑応答がなされました。また、四川外国語大学、福州大学では加藤教授による模擬授業「『源氏物語』とはどういうものか?」、重慶師範大学では小秋元教授による「日本の古典文学に触れてみよう―『平家物語』を中心に―」が実施されました。いずれも日本の古典文学に関する講義でしたが、聴講者の反応は大きく、3大学の学生の皆さんの日本語・日本文化に対する理解度の高さが伝わってきました。
なお、訪問時には各大学の教職員、学生の皆さんに歓待していただきましたことを、この場を借りて御礼申しあげます。四川外国語大学、重慶師範大学、福州大学のさらなる発展を祈念します。

四川外国語大学におけるネルソン教授、加藤教授による進学説明会。同大学ではすでに本年3月に第1回入試を実施し、現在、5名の合格者が特別研修生として修士課程入学に向けた事前研修を法政大学で受けています。
重慶師範大学における進学説明会。半田朋之大学院課入試担当の説明を聞く学生の皆さん。2年生から4年生まで、100名近い参加者がありました。

福州大学における加藤教授の模擬授業。終了後、学生の皆さんから熱心な質問がありました。福州大学で本学科教員が実施する模擬授業は、去る3月につづいて2度目になります。