10月11日(水)13:30より、大学院日本文学専攻の修士論文事前発表会が行われました。発表を行ったのは、今年度に修士論文の提出を予定している14名の大学院生。当日は、日本文学科の教授陣はもとより、他学年の院生や学部生からも活発な質問・コメントが寄せられ、修士論文の執筆を予定している大学院生にとっては大変有意義な会になりました。

s20121010_ip_011 posted by (C)法政日文
| 日曜日, 11 1月 2026 - 17:00 |
10月11日(水)13:30より、大学院日本文学専攻の修士論文事前発表会が行われました。発表を行ったのは、今年度に修士論文の提出を予定している14名の大学院生。当日は、日本文学科の教授陣はもとより、他学年の院生や学部生からも活発な質問・コメントが寄せられ、修士論文の執筆を予定している大学院生にとっては大変有意義な会になりました。

s20121010_ip_011 posted by (C)法政日文
去る6月に実施された平成24年度の日本語検定にて、日本文学科が文部科学大臣賞を受賞しました。日本語検定とは、日本語の総合的な運用能力を測るために敬語・語彙・漢字・表記・文法・意味の6領域から出題される検定試験であり、日本文学科では、昨年から団体受験登録を行っています。受験料がかかるので、あくまでも希望者のみを募って受験していますが、今年は約30名の受験希望者があり、うち7割が1年生でした。
近年では、企業による新入社員研修をはじめ、各種研修の一環として日本語検定の需要が高まっているそうです。日本文学科でも、いえ、日本文学科だからこそ、学生の皆さんには社会に出る前に正しく美しい日本語を身につけて頂きたいと思います。既に第2回(11月10日実施)の受験申込も始まっていますので、受験希望者は尾谷研究室まで受験申込書を取りに来て下さい。 (尾谷昌則)
今月、第44回新潮新人賞の発表が行われ、大学院日本文学専攻を2011年3月に修了した門脇大祐さんが見事受賞致しました。門脇さんは、大学院では旧堀江ゼミに所属し、埴谷雄高について研究していましたが、修了後は文筆活動に転じ、今回の受賞となりました。
新潮新人賞は、その後の芥川賞作家、直木賞作家をはじめ、多くの著名作家を見出した由緒ある賞であり、門脇さんも今後の活躍が大いに期待されます。受賞作品「黙って喰え」は、各選考委員の方々の選評と併せて、2012年10月6日発売の『新潮』11月号にて掲載される予定だそうです。
千葉市立土気南小学校教諭の矢野碧さん(1999年度卒業、2002年度修士課程修了)が、このたび第32回千葉市教職員教育研究発表会(論文の部)で最優秀賞を受賞しました。
矢野さんは、新学習指導要領に「伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項」が加わったことを受け、小学3年生を対象に「俳句」と「ことわざ・慣用句」に親しむ授業を1年間かけて展開しました。その成果を論文「伝統的な言語文化に楽しく親しむ子どもの育成―日常的な取組を生かした授業実践を通して―」にまとめ、このたびの受賞に輝きました。
現在、矢野さんは小学4年生の担任として、「落語」に親しむ国語教育を実践中です。日本文学科・日本文学専攻で学んだことを生かし、さらに活躍してくださることを願っています。
なお、受賞論文は千葉市教育センターのホームページで閲覧することができます。
標記発表会を下記のとおり実施します。本年度、修士論文を提出する学生は、準備をお願いします。また、課程・学年にかかわらず多くの学生が出席することを望みます。大学院進学を考えている学部生(他大学を含む)の参加も歓迎します。
日時 10月10日(水)13:30~18:20(終了時間は予定)
場所 大学院棟202教室
発表者は以下の要領で準備をしてください。
・1人の発表時間は5分です。研究内容を要領よくまとめて発表してください。発表後、10分程度、質疑応答を行います。
・レジュメを準備してください。A4、2枚以内とします。レジュメは9月26日(水)から10月1日(月)13時までの間に、80年館8階、日本文学科共同研究室に届けてください。
法政大学国文学会の機関誌『法政文芸』第8号が6月に、『日本文学誌要』第86号が7月に、それぞれ刊行されました。
『法政文芸』第8号は、藤村耕治教授・中沢けい教授・田中和生准教授の指導のもと、伏見亮祐学生編集長ほか、総勢40名以上の学生編集委員によって完成しました。特集は「当世学生気質」です。
『日本文学誌要』第86号は、専任教員の論文・研究ノート計3編のほか、優秀な卒業論文3編を収載しています。
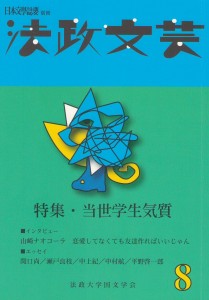
「東京新聞」川崎版で小説『うるみん』を連載中の修士課程1年、結木貴子さんの紹介記事が、法政大学の公式ウェブサイト上の「法政ジャーナル」に掲載されました。結木さんの作品に対する思いや日本文学専攻「文芸創作研究プログラム」への感想も記されています。皆さん、ぜひご一読ください。
東南アジアを中心に活躍されている画家で2011年度日本文学科(通信教育部)卒業生の山田陽子さんが、作品を法政大学に寄贈され、その除幕式が8月1日、ボアソナード・タワー26階ラウンジで行われました。
東日本大震災で亡くなられた方々への鎮魂の思いをこめて描かれた「満月のセレモニー ―祈り―」。
東南アジアの舞踊にも造詣の深い山田さんは、しばしば舞踊を絵のモチーフとして描いてこられたそうですが、この絵を描く際には、両手を合わせて祈る踊り手の表情に大変苦心されたそうです。
どうぞ、皆さんもボアソナード・タワーのラウンジに来られた時には、ぜひ間近でじっくりと鑑賞してください。
山田陽子さんのプロフィール、寄贈絵画除幕式の様子については、「法政フォトジャーナル」に詳細な記事がありますので(下記リンク先)、そちらもどうぞごらんください。
通信教育部2012年度夏期スクーリングが7月30日から始まり、夏期一斉休暇期間をはさんで、8月21日から3群が始まりました。
厳しい残暑の中、大変だと思いますが、もう一息がんばっていきましょう!
さて、今年度も、夏スクの授業風景を動画でお伝えします。
1群「論文作成基礎講座Ⅱ」は、リポートや卒業論文を書くための基礎的な知識を学ぶ授業です。この授業では論文の要約や小論文の作成を行い、教員の添削を受けながら、「大学で求められるリポート・論文とは何か」ということを実践的に学習していきます。
2群「日本言語史」は、日本語の歴史的変遷とそのメカニズムについて学習する授業です。授業におじゃました時には、「ハマナス」の語源に関する問題が取り上げられていました。
すでに連絡していますように、2013年度から通信教育部が大きく変わることとなり、スクーリングも、学生のみなさんが、より受講しやすい形に変更されることになりました。
自分のライフスタイルにあわせて学習計画を立て、スクーリングを受講してみてください。
〈2013年度入学試験科目・日程〉
〈過去の志願者・合格者数〉
この特別入試は、日本の文学・言語・芸能について関心を持ち、文学部日本文学科で学ぶことを希望する、出願資格を満たしたすべての高校生に応募の機会が開かれています。
特に日本文学科では、
などを広く求めています。
志望される方には、これまでの読書経験や日本の文学・言語・芸能への関心などを踏まえ、「何を学びたいか」「なぜ応募したのか」を明確に記入した志望理由書を提出してもらい、第一次選考として書類審査(調査書、志望理由書)を行い、その合格者に対して第二次選考(筆記試験「国語」、面接)を行います。
(1) 以下の①②③のいずれかに該当する者。
① 高等学校または中等教育学校を2013年3月卒業見込の者。
② 通常の課程による12年の学校教育を2013年3月修了見込の者。
③ 学校教育法施行規則第150条の規程により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると2013年3月までに認められる見込の者。
(2) 本学科を第一志望とすること。
(3) 高等学校もしくは中等教育学校後期課程(前期課程は含まない)3年1学期まで(前・後期制の場合は前期まで)の調査書の全体の評定平均値が3.8以上であること。
詳しい入学試験要項、出願書類等はこちらをご覧ください。受験生のみなさんの積極的な出願をお待ちしています。