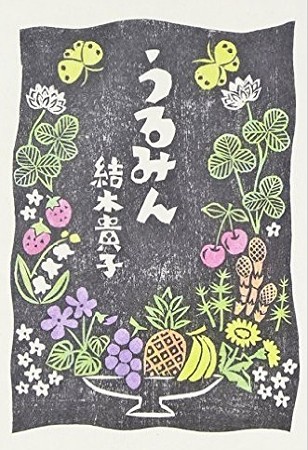3月24日に行われた学位記交付式で、第一回文学部同窓会特別奨励賞の授賞式が行われ、卒業生の加藤寿一さんが受賞されました。
同賞は文学部同窓会が今年度から始められた学生に対する顕彰制度の一つで、在学生の中から学科で一人、さまざまな分野において特にユニークな活躍が認められる人が選ばれ、贈られるものです。
加藤寿一さんはバスケットボール部に所属し、法政のエースとしてチームを牽引し、関東大学リーグでは法政を1部昇格に導きました。また、関東大学バスケットボール選手権ではスリーポイント王で優秀選手賞を獲得する活躍を見せました。そして、卒業後はNBL(ナショナル・バスケットボール・リーグ)に所属する、アイシンシーホース三河のプロ選手になります。
 在学中の目覚ましい成果と、今後のさらなる活躍を祈っての選出・授賞となり、加藤さんには賞状と記念品、奨励金が贈呈されました。
在学中の目覚ましい成果と、今後のさらなる活躍を祈っての選出・授賞となり、加藤さんには賞状と記念品、奨励金が贈呈されました。
第一回文学部同窓会特別奨励賞を加藤寿一さんが受賞されました
2016年3月26日 | Author: nichibunka