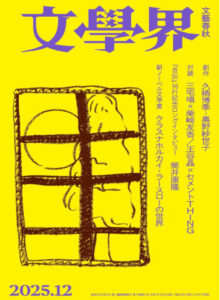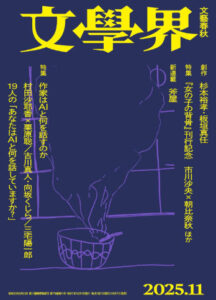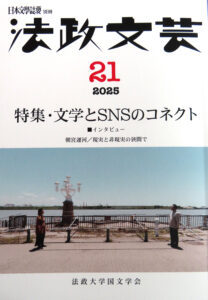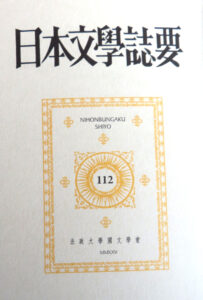2025年度国文学会大会は、9月27日(土)13:30より、富士見ゲート5階 G503にて、対面とZoomを併用したハイフレックス形式にて開催されました。
勝又浩会長による開会の挨拶では、現在大ヒット上映中の映画「国宝」の原作者であり、法政大学経営学部卒業生の吉田修一氏が、芥川賞を受賞した際に記念として撮影されたツーショット写真を持参され、「法政大学にゆかりのある作家が活躍していることはうれしいことです」。と述べられました。
研究発表は、2024年度法政大学大学院修了生(中丸ゼミ)であり、現在総合研究大学院大学日本文学研究コース博士後期課程1年の宮本しえりさんにより、「幸田露伴「対髑髏」論」という題目で行われました。発表では、多くの資料を用いて、幸田露伴の代表作の一つである「対髑髏」への新しい意欲的な考察がなされました。
講演は、2025年度から日本文学科へ着任された森陽香先生により、「古代と古代性と」という題目で行われました。『古事記』上巻冒頭部分の神の名から始まり、具体的な資料と〈言葉〉から、〈古代〉の人々の〈古代性〉について、明快にお話しいただきました。
続いての講演は、2025年度末をもって定年退職なさる中丸宣明先生により、「自然主義の形成と十九世紀文学」という題目で行われました。〈自然主義文学〉と〈十九世紀文学〉の繋がりについて、作家や作品に焦点を当てたいつもの中丸節で大いに盛り上がり、会場は和やかな雰囲気に包まれました。なお、当日の発表・講演の詳細な内容については『そとぼり通信』第70号および『日本文學誌要』113号に掲載予定です。
 総会では、2024年度の会務・会計報告と本年度の会務案・予算案、役員案が審議・承認され、その後閉会となりました。
総会では、2024年度の会務・会計報告と本年度の会務案・予算案、役員案が審議・承認され、その後閉会となりました。
大会終了後には、富士見ゲート3階カフェテリアつどひにて、懇 親会が催されました。会員、教員や卒業生も含めた学生たちに多数ご参加いただき、賑やかに始まりました。勝又浩会長、堀江拓充先生をはじめ、中丸宣明先生、森陽香先生、宮本しえりさんからお話いただきました。その後は、その場にいらした坂本勝先生のゼミ生から、退職後の充実された興味深い暮らしについて、また歴代の中丸ゼミ生からは、思いがけない愉快な中丸先生エピソードが次々と飛び出し、盛会のうちに終了しました。
親会が催されました。会員、教員や卒業生も含めた学生たちに多数ご参加いただき、賑やかに始まりました。勝又浩会長、堀江拓充先生をはじめ、中丸宣明先生、森陽香先生、宮本しえりさんからお話いただきました。その後は、その場にいらした坂本勝先生のゼミ生から、退職後の充実された興味深い暮らしについて、また歴代の中丸ゼミ生からは、思いがけない愉快な中丸先生エピソードが次々と飛び出し、盛会のうちに終了しました。